中遠見山付近から見た五龍岳 点線は北尾根
小目次
4節−1 ルートの概要・考察
4節−2 気象の分析
1、事故時の気象実況
2、解説と分析
3、何が事故につながったのか
第4節−3:同時期に入山していた他パーティーからの情報
1、他パーティーからの情報のまとめ
2、他パーティの行動記録
第4節−4:彼等の辿ったルートの推察
第4節−5:事故発生日時の推察
第4節−6:事故発生状況の推察
はじめに
今回の遭難事故では、コースタイムのメモ、カメラ、トレース等が全く無く、また天気図や食糧など多数の装備が行方不明になっていることから、彼等が実際に取った行動、及び彼等が実際に得た情報が明らかでない。
そこで第一に、彼らが計画していたルートの実踏調査を行った。
第二に、今回の事故には、悪天候が大きく影響していると思われるため、気象の調査・分析を行った。
第三に、同時期に同山域に入山していたパーティとテレキャビンの職員からの聞き取りを行った。しかしこの調査でも、確実に彼ら二人をみたという目撃情報は得られなかった。
この節では、これら三つの調査・分析と、遺留品、遺体の発見場所等の情報を基に、彼らの行動を推測しているが、あくまでも推察の域を出ないことを念頭において読んでほしい。
両名が計画していたルートは、テレキャビン終点より遠見尾根を経て大遠見山付近の支尾根、もしくは西遠見山付近の支尾根から白岳沢・カクネ里出合に下降し、北尾根に取り付き、五龍岳山頂を通って、再び遠見尾根を経て下山するというものであった。
ガイドブックの情報を統合すると、このルートの概要は以下の通りである。
五龍岳北尾根は国境稜線より白岳沢とカクネ里の出合まで伸びている大きな尾根で、無雪期は潅木に覆われているが、積雪期にはキノコ雪をつけた急峻な雪稜になる。テレキャビン終点から大遠見山付近の下降点までは悪い所はなく問題はない。
白岳沢・カクネ里出合へは大遠見山付近から伸びている支尾根を下降しする。この下降には西遠見山付近の支尾根からでも可能である。北尾根へは尾根末端のルンゼから取り付くが雪壁になっている。D沢に伸びる尾根の分岐点までは急なナイフエッジで中間に壁もあるが、上部は幅のあるゆるい尾根になり、最後は国境稜線直下の雪壁を登り、北尾根の頭に抜ける。
北尾根の頭から五龍岳までは、岩と氷の入り交じった急斜面の岩稜となる。G5・G4のコル、G4・G3(五龍岳頂上)のコルは風の吹き抜けが強く、荒天になると下手な岩壁登攀よりも更に厳しいものになる可能性が高い。
五龍岳から五龍岳山荘にかけては、好天ならさほど問題はないが、視界が悪かったり荒天になるとザイルを必要とする事がある。
五龍山荘からの遠見尾根の下降は難しくない。
我々は彼等が辿ったと思われるルートを実踏し、検証をした。以下はその記録である。(関、浅田 記)
1999年5月2日 快晴
テレキャビン、リフトと乗り継いでリフト終点へ。こんなに簡単に高度をかせいで良いのだろうかと思いつつも、体力の落ちた今の自分にとっては有り難い。気持ち良さそうなスキ−ヤ−を横目に見ながらリフト駅を出発し、慰霊碑が立ち並んだところから一旦下り、雪面を登り返して遠見尾根へ出る。遠見尾根自体は傾斜もなく、新雪のラッセルだったら大変であろうが、五月の連休ということもあり、バケツ状になった踏み跡を順調に進み、途中特に問題になる箇所もなく、大遠見山を越え西遠見に着く。
西遠見から白岳沢への下りは、地図上でもはっきりとわかる尾根から下りに入るが、すぐに横の、冬でも状態が良ければ使えると思われる大きなルンゼの斜面に入り込み、尻セ−ドで一気に白岳沢に下り立つ。
白岳沢は完全に雪に埋まっており、沢も広いため上部からのブロックの心配もあまりなく、左岸からA沢、B沢、C沢出合いを過ぎ、D沢出合いの先で北尾根への枝尾根へと雪の詰まった小さなルンゼから取り付く。急な雪壁になったルンゼと雪稜とをつないで高度を稼ぐが、雪が落ちて垂直な藪登りとなる部分もかなり多く、苦労させられる。
北尾根上に出てからは急な雪壁とナイフリッジの登りとなるが、朝からの日差しで午後からの雪の状態は最悪で、意外と時間がかかってしまう。傾斜の落ちた雪稜上を踏み固めて、テントサイトとする。(西遠見とほぼ同高度と思われる)
1999年5月3日 曇り
ここより上部は藪に悩まされることはないが、雪壁や雪稜に亀裂が発達してきており、時期によっては進退窮る場合もあると思われる。(以前に当会の会員が登った時に、主稜線直下の亀裂が処理できずに北尾根を再び下降したことがあった。)今回は、なんとか雪壁、雪稜をつないで主稜線へと抜けることができた。
主稜線上は強風のためか登山道が出ており、途中でアイゼンを外して進む。五龍岳は見えているのだが思ったより遠く、技術的に問題はないが、強風雪の中ではかなり厳しいだろうなと思いながら進み、再びアイゼンを着けて五龍岳の頂に立つ。
五龍岳より稜づたいに約100M下った地点で、彼等のザックが見つかった場所だとすぐに特定できる岩棚へ着く。ツエルトを被ってビバ−クするには、広さ的には問題ないが、強風の中では遮るものが無いため、かなりしんどそうな所だ。
ここより五龍山荘へは約30分で下り、山荘からは白岳を登らずに雪面をトラバ−スして遠見尾根へ出て、あとはひたすらトレ−スを下り、テレキャビンにて下山する。
どこの山へ行ってもそうだが、特に雪山の場合、雪の量、質、天候、風、視界等で、全く違った山になってしまうものであり、彼等がおかれていた状況を簡単に推察することはできなかった。
中遠見山付近から見た五龍岳 点線は北尾根
気象概況
彼らが事故に遭ったと思われる3/21〜3/22には、俗に言う「二つ玉低気圧」が発生し、日本列島の上を通過している。この気圧配置は、山岳地帯に悪天候をもたらし、気象遭難を引き起こすとしてよく知られている。
聞き取り調査(第4節−3)から気象に関する記述を書き出すと以下のようになる。
3月20日 朝 曇り 小雪が舞う程度 風は弱い
夕方〜 天候回復 星も見えた
21日 朝
高曇り 山も見えていた
11時頃〜 天候が崩れ出す これ以降天候はずっと下り坂
12時頃
五龍岳頂上付近は風雪が強く、視界は50m位
24時頃
風向きが南西から北に変わり、今まで以上に一段と強い風になる
22日 9時
五龍とおみスキー場テレキャビン山頂駅での実測で、風速15〜30m/秒
15時
同風速15〜45m/秒
山頂駅の少し上のリフト管理小屋では最大瞬間風速50m/秒以上になった
この天候は夜になるまで収まらなかった
ピークより1000m以上標高の低い、テレキャビン山頂駅で、気象用語でいう、暴風(24.5〜28.4m/秒)、烈風(28.5〜32.6m/秒)を超える颶風(32.7m/秒〜)が記録されているのだ。風速45m/秒という、風力段階も付けられていない、まさに想像を絶する風が吹き荒れていたのである。
稜線上では耐風姿勢など関係なく、山と一体化しているもの以外は全て飛ばされてもおかしくない風だったのではないか。
しかも、風だけではなく、おそらく飛ばされた雪も舞っていただろうし、この風によって体感温度は非常に下がっていたはずで、この時間帯に稜線付近に二人がいたとすれば、非常に過酷な状況だったことは間違いない。
今回、事前にある程度の悪天候は予想されていたが、聞き取り調査した中でも、二つ玉低気圧の発生を把握していたパーティはほとんどおらず、天候がもう少しもつと判断して入山したと思われる。
なぜそのような判断につながったのか、天候の推移と分析、さらに「思ったよりも早く天候が崩れた」原因についての考察を行った。
八方尾根ゴンドラ山頂駅付近の環境庁気象観測用ロボット(自動測定器)の気象データ
<グラフの見方>
・グラフは横軸に時間、縦軸に風速と降水量をとっている。
・左の縦軸の目盛りが風速、右の縦軸の目盛りが1時間ごとの降水量を表す。
・細線が風速の変化を、太線が降水量の変化を表す。(データは1時間ごとにとっている。)
・風速と降水量は、それぞれが判別しやすようにゼロ点をずらしてある。
・グラフの上辺には、4時間ごとの風向きが示してある。
・グラフ中の文字は、推定される彼らの行動を表している。
20日のデータを見ると、日中は降水があり、夕方には降水が終わっていることがわかる。このことは、他パーティーからの聞き取り調査(第4節−3)の、遠見尾根では日中軽い降雪があり、夕方から天候が回復したという情報と一致している。
21日のデータを見ると、昼12時前から降水があり、風が吹き始めていることがわかる。21日の天候が崩れだしたのは、11時ころからという他パーティーからの情報と一致している。
21日昼前から吹き始めた南風は、21日夜から22日6時ごろまでの間、一旦風が弱まる。そして、北寄りに風向きを変え、風速は22日の夜にかけてどんどん強まり、22日21時には風速31.3m/sに達している。瞬間的な最大風速はこの値よりさらに大きかったと考えられる。聞き取り調査からは、22日は歩くのも困難なほどの強風だったということがわかっている。
五龍とおみスキー場テレキャビン山頂駅の気象データ
| 日時 | 風速・風向(m/s・16方位) | 気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 湿度(%) | 降雪(cm) | 積雪(cm) | 視界(km) | 天気 |
| 3月19日9時 | 南2−5 | 5 | 3 | 74 | 0 | 260 | 10 | 雨 | |
| 3月19日15時 | 西2 | 6 | 7 | 73 | 0 | 255 | 10 | 曇 | |
| 3月20日9時 | 0 | -5 | -4 | 75 | 1 | 255 | 0.1 | 雪 | |
| 3月20日15時 | 北東0−3 | -4 | -4 | 73 | 3 | 255 | 0.3 | 雪 | |
| 3月21日9時 | 0 | -4 | -5 | 65 | 0 | 255 | 30 | 曇 | |
| 3月21日15時 | 北東0−5 | -3 | -3 | 71 | 1 | 255 | 0.5 | 雪 | |
| 3月22日9時 | 北15−30 | -9 | -9 | 73 | 25 | 280 | 0.05 | 小雪 | |
| 3月22日15時 | 北西15−40 | -10 | -3 | 75 | 0 | 280 | 0.05 | 小雪 | |
| 3月23日9時 | 北東0−3 | -9 | -12 | 71 | 1 | 280 | 20 | 晴 | |
| 3月23日15時 | 0 | -2 | -2 | 67 | 0 | 280 | 40 | 快晴 |
Fig1 21日3:00の天気図
20日に雪を降らせた低気圧が東に去り、続く移動性高気圧に覆われて日本付近は穏やかな天気となっている。朝鮮半島付近には低気圧があり、今後発達し悪天候をもたらすことが予想される。
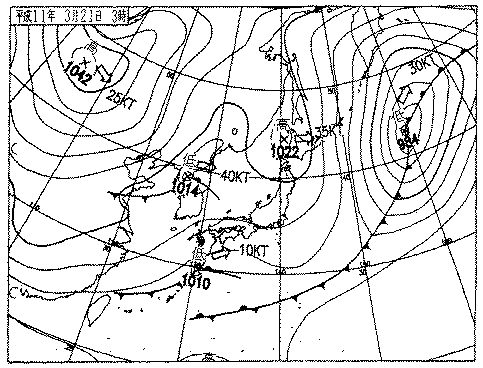
Fig2 21日9:00の天気図(高層含む)
大陸には1040hpの高気圧があり、低気圧が発達することが予想できる。また南海上にも弱い低気圧が発生しているが、この時点で二つ玉低気圧になることは予想しづらい。高層天気図では気圧の谷の後ろに強い寒気が控えており、低気圧の発達が予想される。南海上の低気圧に対応する上空の気圧の谷はまだはっきりしていない。
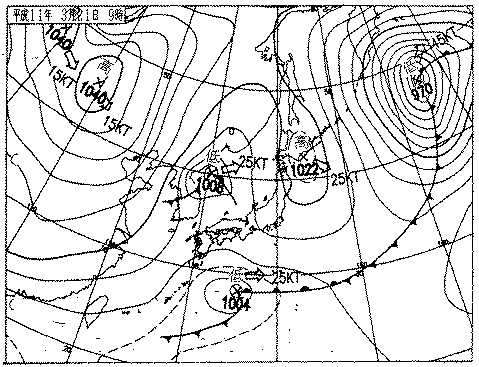
Fig3 21日15:00の天気図
前の天気図との間で、日本付近を温暖前線が通過している。聞き込み調査でも、昼前後から天気が急に悪化したとの証言がなされている。温暖前線の構造上、地上天気図上での前線の位置よりも山岳地域では影響が早めにあらわれる。
この時低気圧そのものはそれほど発達していなかったのに急に風が強まっている。原因として、動きの遅い東海上の高気圧に向かって低気圧が東進を続けたため、気圧傾度が急に大きくなったことが天気図上から読み取れる。
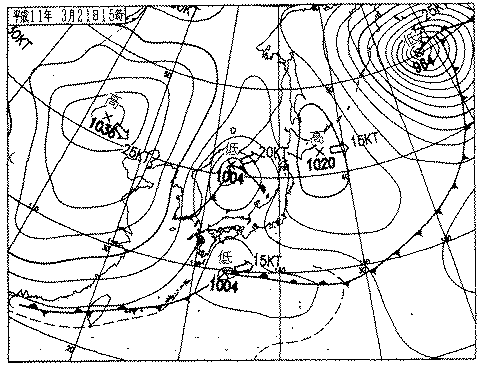
Fig4 21日21:00の天気図 (高層含む)
二つ玉低気圧の様相がはっきりしており、高層天気図でも気圧の谷が急速に深まっている。
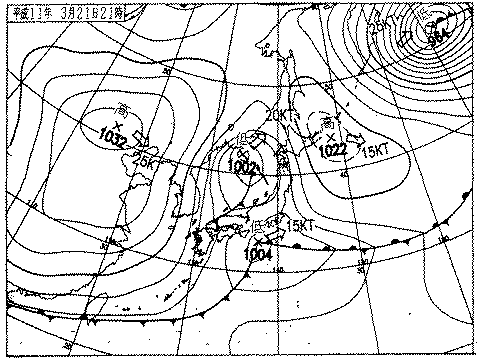
Fig5 22日3:00の天気図
地上図上での寒冷前線の通過と低気圧の発達。聞き取り調査でも、「夜半過ぎからさらに風雪が強まった」との報告がある。
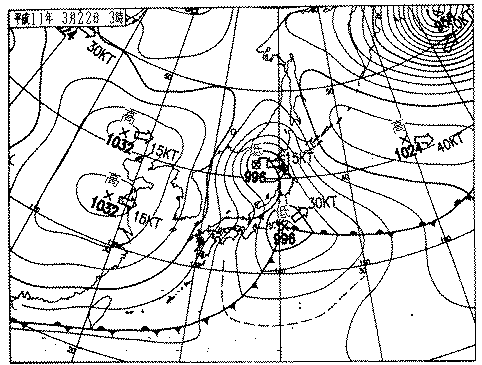
Fig6 22日9:00の天気図(高層含む)
冬型の気圧配置。高層天気図上では上空の気圧の谷が9:00前後に通過している。
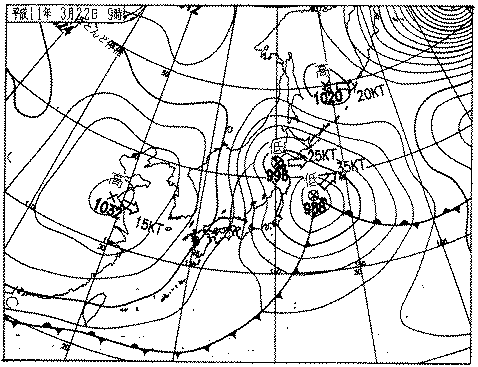
「冬山」と比べた場合、「春山」のほうが気温が高く雪も落ち着いており快適な山行となることが多い。そのため「冬山」をこなしてから臨む「春山」にたいしては、どうしても緊張感や危険に対する意識が低下しがちである。しかし気象の変化に関しては「春山」のほうがよっぽど激しく、「冬山」とは違った危険の要素が多くある。
今回の事故も、彼らが実際にどの様な情報を入手し、どう判断し、どう行動したかが不明なため、正確な原因の追求は不可能であるが、春山気象ならではの危険を回避できなかったケースと言えるのではないだろうか。
同じ時期に同地域を登っていた他パーティからの聞き込み調査では、多くのパーティが「21日に思ったより早く天気が崩れた」という証言をしている。そして実際にいくつかのパーティは、下山日が大幅に遅れるなどの状況に陥っている。
ここでは、平松・石原パーティも他パーティ同様に「思ったより早く天気が崩れた」ことが原因のひとつになって事故につながったと仮定し、気象の考察をする。
・なぜ思ったよりも早く天気が崩れたのか?(幾つかの仮説)
<仮説1:天気予報と比べて山岳地域の天気の崩れが早かった>
地上向けの天気予報よりも、山岳地域での天候の悪化は早めに起こることが多い。特に冬よりも春にこうした傾向があらわれる。(講習会の中では、温暖前線の構造を理由のひとつとして説明している。)
今回の例でも、山では21日の正午前後から天候が悪化しているが、同日午後3時のスキー場の気象観測データではそれ程強い風は吹いていない。21日の昼間は上空の気圧の谷が急速に深まったため、上空(山)では強風になったと考えられる。天気予報はあくまでも地上向けの内容であることを意識して、山での天候の変化を予測しなければならない。
<仮説2:天気の変化が急激であったため「早い」と感じた>
20日の夜から21日の朝に関しては天候は比較的安定していた。この安定した天候に後押しされる形で頂上アタックを決定したパーティも多かったと思われる。その後半日もかからずに天候は急速に悪化するわけだが、変化の度合いが急であったために「思ったよりも早く天気が崩れた」と感じたパーティもいたかもしれない。
<仮説3:天気予報がはずれ、実際に天気の崩れが早まっていた>
まずは事実として、長野県で荒れ模様になったのは22日になってからだが、雨や雪は松本やスキー場で昼過ぎから降り出していて、確かに前日までの天気予報より天気は早く崩れている。
21日は日本海の低気圧が急速に発達を始めたため、天気の崩れるタイミングを天気予報が的確に捉えていなかった可能性が考えられる。登山者としては「低気圧情報」で「今夜から大荒れ」といった場合でも夕方までは大丈夫とは考えないで、前後にずれる可能性がある事を考えて行動する必要がある。
聞き込み調査のねらいは、入山していた平松・石原パーティーがどのようなルートを取り、どのような行動をしたかを裏付ける目撃情報を集めることだった。
また、この時期日本を襲った二つ玉低気圧による悪天候が、北アルプスの山中では実際にはどのような状況をもたらしたかを、この悪天候を体験したパーティーへの聞き取り調査を進めることによって明らかにしたいと考えた。この悪天候に対して各パーティーがどのように判断し行動したかも、できるだけわかるよう調査を行った。
(個々のパーティーから聞き取った情報は、第4節−3−2参照)
3月20日
朝方(入山予定時)の天候は曇り。小雪が舞う程度。風は弱い。特に行動に支障のある天候ではないと思われる。この日はどのパーティーも順調に行動している。
テレキャビンの始発は8時15分である。8人乗りで12秒に1台運行しているので、テレキャビンに乗れなくて出発が遅くなることはないと考えられる。朝、入山したパーティーは9時までには入山している。入山パーティーは多かった。
遠見尾根を行く間、ラッセルの必要はない。積雪状態はトレースを外すとスネまでもぐるくらい。
山岳ガイド・増井氏が地蔵の頭の少し先で、若い感じの2人パーティー(少々重装備)に追い抜かされている。
山岳ガイド・志水氏のパーティーはこの日、天場の大遠見に着いた時点で先行しているパーティーはほとんどなかったと言っている。グラフ(1)から増井パーティーはその志水パーティーより先行しているので、先に見た2人パーティーが平松・石原パーティーだとすると、平松・石原パーティーは志水パーティーより早く大遠見に着いていたことになる。
当時の天候の聞き込みから、20日は17時頃までガスが濃く、谷には下れない状況だったと推測される。しかし、大遠見から北尾根への下降点付近にテントを張った志水パーティーはその時点ではその他のパーティーを見ていない。また、谷に下っていくトレースも目撃されなかったという。増井パーティーが目撃したのが、平松・石原パーティーだとすると、大遠見山の下降点付近以外にテントを張った可能性が高い。増井パーティーの目撃が平松・石原パーティーではなかった場合、2人は遅れて志水パーティーがテントを張った場所に着いた可能性もある。
夕方から天候が回復。星も見えていたらしい。この日のうちに、二つ玉低気圧の発生を明確に予想していたパーティーはいない。
3月21日
朝の時点で天候は高曇り。山も見えていた。谷には下降可能な天候。
1999年3月21日8時頃 遠見尾根中程からの五龍岳(磯谷真規氏撮影)
グラフ(2)を見るとわかるように、朝6時頃までに遠見尾根から行動を開始したパーティーは皆、21日中に下山している。予定を変更し、悪天を見越して早めに下山したことになる。それより出発が遅めだったパーティーは、悪天に巻き込まれることになり、21日中に下山する余裕はなかったものと考えられる。
志水氏は、当初平松・石原と同じ北尾根ルートを計画していたが、遠見尾根の雪の状態から北尾根も時間がかかり、天候が荒れないうちに安全圏までたどりつけないことを考え、北尾根を中止し、ルートを変更している。
平松・石原パーティーが北尾根ルートへ行った場合、予想以上に行動に時間がかかり、結果的に遠見尾根の天場を遅く出たパーティーと同じような状態になったことが考えられる。
一方、この時の雪質に関しては、鹿島槍ケ岳天狗尾根を登っていた四大学山岳部合同パーティーによると、クラスト気味でラッセルは全くなく、ルートを外しても足が潜るということはなかったという情報もある。北尾根も同じような雪の状態であったことも考えられる。
6時15分に出発した志水氏は、出発までにテントを張った下降点から、谷へ下るトレースは見ていない。
前日の天候と合わせて考えると、平松・石原パーティーは大遠見以外の下降点にテントを張ったか、大遠見から下ったとすれば、志水パーティーが出発した時刻以降に下降を開始したと思われる。
平松・石原パーティーが下降するとすれば、大遠見山付近、もしくは西遠見山付近からと考えられる。しかし、志水氏は大遠見山から白岳に至る間で、谷に下っているトレースは見ていない。また、下降適地もなかったと言っている。
場所にもよるが、おおよそ午前11時頃から天候が崩れだしている。これ以後、天候はずっと下り坂。ほとんどのパーティーが天候の悪化を予想していたが、その予想より実際には早く崩れている。
二つ玉低気圧の発生をはっきりつかんでいたパーティーは聴き取りをした中にはほとんどおらず、二つ玉低気圧発生を把握していたと答えた都職山の会でも、21日の朝の時点で初めて認識している。
熊本学園大パーティーおよび桑原パーティーが12時頃山頂付近で、数人のパーティーに出会っている。その数人パーティーは、軽装で男女のパーティーだったとの目撃情報およびグラフ(2)から、奈良岳志会パーティーの可能性が高い。
上記3パーティーは山頂から遠見尾根への下降中に登ってくるパーティーには会っていない。遠見尾根側から最後に五龍岳に登頂したパーティーは奈良岳志会パーティーだったと推測される。奈良岳志会パーティーが西遠見山の幕営地に戻ったのは夕方5時を回っている。
こうした点から、平松・石原パーティーが遭難地点に到達したのは、21日昼12時以降であると考えられる。
昼12時頃には、五龍岳頂上付近は風雪が強く、トレースもすぐ消えてしまう状態だった。視界は50m以下。山頂からの下山は、度々ルートを見失う状況だった。
15時頃、視界がさらに悪くなり、大遠見付近では、ルートを誤りそうになったパーティーが出ている。
21日の天候は、かなり風が強くなっていたが、22日のような頻繁に耐風姿勢を取らなければいけないほどの強風ではなかったという。
グラフ(2)を見ても、五龍岳登頂時刻が遅く、天候が崩れだしてから五龍岳を下山した桑原パーティー・熊本学園大学パーティーは、午前中の天候が崩れないうちに五竜岳を下った他パーティーに比べて特に行動時間がかかっていない。
五龍岳の南に位置する鹿島槍ケ岳東尾根を登っていた船橋勤労者山の会によると、11時前から天候は崩れだしていたが、稜線に出るまではそれほど強い風は感じなかったという。稜線に出てからは、何度か耐風姿勢を取らなければならなかった。
このことから、北尾根に取り付いたとすれば、その間はそれほど強い風を感じなかったが、鹿島槍ケ岳〜五龍岳の稜線上に出るとかなりの強風にみまわれたと考えられる。
夜中の0時頃、風向きが南西から北に変わり、今まで以上に一段と強い風になる。風向きの変化は低気圧の通過によるものと考えられる。
3月22日
白馬五竜スキー場では、朝7時50分の段階では風速20m/s以上でテレキャビンの営業運転は不可能だった。その後9時30分頃には風が強まり、運行基準では完全に運転不可となる風速25m/sを超えた。スキー場は終日閉鎖となった。
テレキャビン山頂駅での実測では、9時に風速15〜30m/sを記録、15時に風速15〜45m/sを記録。山頂駅のさらに少し上にあるリフト管理小屋では、最大瞬間風速で50m/s以上になった。テレキャビン職員の話では、12年間で4回ほどしか経験したことない悪天候だったという。
遠見尾根の北にある八方尾根のゴンドラ山頂駅付近にある自動測定機の気象データによると、21日昼前から段々強くなった風は、いったん弱まるが、22日午前6時ころから再び強まり、21時には風速31.3mを記録している。
大遠見より下(地蔵の頭寄り)の遠見尾根上でも、強風のため歩いているより止まっている時間の方が長いような状態だった。耐風姿勢を取っていても動かされてしまうほどで、吹雪でまともに目も開けていられない状態であった。
この天候は夜になるまで収まらなかった。
大遠見の天場を午前8時過ぎころ出発した熊本学園大学パーティーのメンバーの一人は、リフトの駅の近くまで来ていたが、地蔵の頭300m程手前で力尽き、亡くなっている。また、横浜山岳会パーティは、メンバーの一人が凍傷にかかった。そのメンバーのため、小遠見でビバークを試みているが、あまりの風の強さにツェルトが広げられないほどの状態だった。
聞き取り調査をした中で、この日に遠見尾根にいたパーティーはすべて、地蔵の頭付近までは降りて来ているが、下山はできずビバークを余儀なくされている。
支尾根である大遠見尾根よりさらに上方で、地形的にも険しい主稜線上では、さらに過酷な天候だったであろう。
3月20日−3月22日、遠見尾根入山パーティーの行動
以下の資料は、平松・石原パーティーと同時期に遠見尾根に入山していたパーティーの行動をグラフ化したものである。
グラフ化するにあたっての基本データーは、各パーティーからの、面会及び電話による聴き取り調査にて得たものである。
従って、データーの精度という点で、抜け、バラツキがあることはやむを得ず、あくまで各パーティーの位置関係を掴む目安と考えていただきたい。
(表及びグラフの見方)
1、表の網掛け部分が各パーティーの行動範囲を示す。
2、表の空欄部分は、時間が不明なためデーターが無い箇所である。
3、グラフは縦軸に時間、横軸に場所をとっている。
4、データーのない部分はその間を自動的に補間してグラフ化している。
6、時間に着目すれば、各パーティー着目すれば、各パーティーがその時間にどの付近にいたのか、おおよその見当がつく。
7、場所に着目すれば、各パーティーがその場所を通過したおおよその時間が分かる。
8、各パーティーのグラフが交差している場所は、理論上はそのパーティーが出会っていることを示すが、データーの精度が低いため断定はできない。
9、表の斜字体はグラフ化のための推定値である。(データーが1点しかなかったため)
グラフ(1):3月20日
グラフ(2):3月21日
グラフ(3):3月22日
都職山の会聞き取り結果
聞き書き日時 :1999年3月27日,4月6日,4月8日
聞き書き相手 :浜中日出男・頓所武伸・本間照治
(敬称略)
パーティー構成:パーティー構成:
備考 :浜中氏がチーフリーダーとして、全パーティーの最後尾を歩行していた。
| 登山計画(予定) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−西遠見山 |
| 3月21日 | 西遠見山−五龍岳−西遠見山 |
| 3月22日 | 西遠見山−地蔵の頭−(テレキャビン)−神城(下山) ※悪天時は21日中に下山 |
| 登山コース(実際) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−西遠見山(C1) |
| 3月21日 | C1−五龍岳−西遠見山−地蔵の頭−(テレキャビン)−神城(下山) |
| 時刻・場所 | 行動・天候・ルート状態・目撃情報・他 | ||
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−西遠見山 | ||
| 7:30
神城 |
[天候] | 曇り.見通しは良い.ほぼ無風.(頓所)
上の方はガスって見えなかった.[上は雪が降っているのでは] (浜中 |
|
| 8:30
地蔵の頭 |
[天候] | 雪がぱらついていた.風は南から南西の風が少し吹いていた. | |
| [ルート状態] | 前日に雨が降ったということで、クラスト状態で歩きにくい.
トレースははっきりしている. |
||
| 10:30 | [天候] | 風が一瞬北西に変わった. | |
| 昼頃 | [天候] | また南からの風吹き出す.あたたかい風が吹き気温が上昇した.雪がちらつく.視界きかず. | |
| 13:00? | [行動] | 西遠見山手前の台地状のところにテントを張る(先行2張り).その後続々と幕営. | |
| 15:00 | [天候] | 風が止む. | |
| 16:00 | [行動] | 気象通報を聞く.大陸に低気圧、太平洋に前線があった.
気象通報では「二つ玉低気圧」の気圧配置になるという言及なし. [大陸の低気圧がゆっくり進めば、単純な西高東低の冬型の気圧配置になるだろう.大陸の低気圧が日本海に近づいて進めば、前線を刺激して、南風が入り込んで大変荒れるだろう.どちらにしても、今後、天気は下り坂である.このような天気図から「二つ玉」になる場合があるとは思ったが、この時点では、「二つ玉」になる、ならないという積極的な判断はしなかった.] |
|
| 17:00 | [天候] | 晴れ始めた. | |
| 19:00 | [天候] | 稜線がくっきり見えた.星も見えた. | |
| 3月21日 | 西遠見山〜五龍岳〜西遠見山〜地蔵の頭〜(テレキャビン)〜神城 | ||
| 4:00
西遠見山幕営地 |
[行動] | 起床. | |
| [天候] | 曇っていたが稜線は見えた. | ||
| 5:30頃 | [行動] | 2〜3局のラジオ天気予報を聞く.予報の内容は・(新潟方面、多分)で午後の遅くから、夜間にかけて荒れる.・大陸の低気圧と南岸に発生した低気圧のうしろから、寒気が流入している.・「荒れる」ということを強調した、警鐘的な感じのする放送だったが、「二つ玉」という言葉は使っていなかった.[二つ玉低気圧の発生を意識.→天候悪化は時間の問題.
22日は天候は荒れるだろうから、本日11時にどこにいるかで、行動を決定する.その時点で頂上を踏んでいなかったとしても、引き返し安全圏に下る.] ※以上の判断は、20日16時の時点では判断できなかった. |
|
| 6:00 | [行動] | 出発. | |
| 白岳稜線 | [天候] | 富山湾の上空に、雲堤がみえた.海の位置は分かったが、海は見えなかった.剣岳の方に、レンズ雲のようなものが見えた.[思ったよりも早いなと感じた。11時判断では甘いかも、と思った.] | |
| 五龍岳稜線 | [天候] | 曇ってはいたが、山の見通しはよかった。風が吹きはじめた.(トラバース気味の稜線を歩いていたので、風向きは分からない) | |
| 9:00?
五龍岳山頂 |
[天候] | 鹿島槍の稜線は見えていた.
ヤッケのフードを被りたくなるくらい、風が強いと感じた.白岳で見た雲が、かなり迫ってきているなと思った.ガスが濃くなってきた.天候の悪化は、初心者でも感じられるくらいだったと思う. |
|
| 五龍山荘 | [天候] | 五龍岳の頂上がガスに入りはじめた. | |
| 白岳下り | [天候] | 稜線がガスに包まれた.風は吹いていた.北西風ではなく、南風だったので、おやっと思った. | |
| 幕営地につく前に雪が降りはじめた | |||
| 11:15
西遠見山幕営地 |
[行動] | テントを撤収.撤収の際、ザックに積もる程度の降雪がある. | |
| [天候] | 尾根上の視界は悪くなり、トレースも埋まりはじめた. | ||
| 大遠見山付近 | [天候] | 南よりの風が吹いていた. | |
| 地蔵の頭付近 | [天候] | 地蔵の頭近くの吹き溜まりでは、かなりの積雪. | |
| 14:00
テレキャビン山頂駅 |
[天候] | 風は止んでいた.
[上の方は真白で、悪天だと思った.] |
|
[その他コメント]
バリエーションをやるようなパーティーは2つほど見た。3〜4人パーティーだった.前に雨が降っていたと聞いていたし、雪がしまっていたので、積雪があったら雪崩れるなと思った.
志水哲也氏聞き取り結果
聞き書き日時: 1999年4月8日
聞き書き相手: 志水哲也
(敬称略)
パーティー構成: 男性3名
(山岳ガイド志水氏、他、男性2名)
備考:
お客さんは各々常連客で冬の白馬主稜を単独でできる実力。予定のコースは遭難した二人と同じ北尾根だったが、五龍岳−八方尾根縦走に切り替えた.
| 登山計画(予定) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見−北尾根−(C1) |
| 3月21日 | (C1)−五龍岳−遠見尾根−(C2) |
| 3月22日 | (C2)−神城(下山) |
| 登山コース(実際) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見(C1) |
| 3月21日 | (C1)−五龍岳−唐松山荘−八方尾根−(下山) |
| 時刻・場所 | 行動・天候・ルート状態・目撃情報・他 | |
| 3月20日 | 神城−地蔵の頭−大遠見 | |
| 8:20?
神城 |
[行動] | 始発(8:15)の次のテレキャビン(8人乗り)に乗る. |
| [目撃] | 特に記憶にあるパーティーはいない. | |
| 8:45
地蔵の頭 |
[行動] | テレキャビン上部のリフトに乗らなかったため先行パーティー多数.(30人くらいか) |
| [天候] | 小雪舞うが、風はない. | |
| [ルート状態] | 先行パーティーのトレースがしっかりついていた.
トレースを外すと、スネくらいまでもぐる状態.[3月としては雪の状態が悪い→北尾根は、ラッセルが大変ではないか] |
|
| 12:45
大遠見 |
[行動] | ここまでにほとんどのパーティーを抜かし、先行パーティーはほとんどいなかった.
その途中、登攀装備を持ったパーティーは見なかった.谷への下降地点(大遠見山の少し西)へテントを張る.北尾根を登るパーティーが通常下りる地点. |
| [天候] | 遠見尾根沿いは少しは視界があったが、谷は雲の中で完全に視界がない.[下りるのは難しい.]北尾根は全く見えなかった. | |
| [トレース] | テントを張り終えてから30分ほど下降点を偵察したが、この下降ルートの尾根を下りるトレースはなかった.この尾根以外のことはわからない.この偵察以降のトレースについてもわからない.この尾根を下れば、音で気付くと思うが、音は聞かなかった。 | |
| [目撃] | この時点で、この辺りに他にテントを張っているパーティーは見なかった.(視界が良くなかったので、近くに他パーティーがいたのかどうかわからないが、少なくとも下降点にはテントはなかった.) | |
| 夕方 | [天候] | 記憶にない.→偵察後にトレースが埋るほどの降雪があったかどうか覚えていない |
| 夜 | [目撃] | テントの外に出た時に他パーティーの声を聞く |
| [天候] | 他メンバーが星が出ていると話していた.
[翌日は1日弱は天候がもつという予報があったので、天候については楽観視.翌朝の天気予報で行動を決めようと思っていた.] |
|
| 3月21日 | 大遠見−五龍岳−唐松山荘−八方尾根−(下山) | |
| 3:30
大遠見天場 |
[行動] | 電話で天気予報を聞く.
21日は昼から風雪となり、22日はもっと悪くなるとの予報.[予想より崩れるのが早く、半日では安全圏まで降りれない.ビバークしても、その後、いつ晴天になるかわからない.98年12月に五龍岳に行ったときに、G0から先の雪の状態が非常に悪かった.]→北尾根を中止.五龍・唐松縦走に切り替え、21日中に下山することにする. |
| 4:00
夜明け |
[天候] | 高曇りまたは晴れ. |
| [トレース] | 天場を出るまで(4:00−6:15)に、谷に下るトレースはなかった.<他パーティーからの情報や気象データからすると、21日午後以降にトレースが埋るほどの雪は降っていない可能性が高い.> | |
| 6:15
天場出発 |
[目撃] | 大遠見から先では、谷に下りるのに適した尾根はなかったし、トレースもなかった。
北尾根も見たが、人影は見当たらなかった. |
| 10:00
五龍岳山頂 |
[目撃] | 北尾根方向はよく見えたが、人影は見当たらなかった.鹿島槍方面からのトレースもついていなかった. |
| 頂上直下のコル | [ルート状態] | 雪洞は掘れない状態.雪洞を掘るなら、長野側に懸垂でもして掘るしかない. |
| 10:45
五龍山荘 |
[天候] | 風と雪が出てきた.[天候は予想より早く崩れた.北尾根に行ったとしても、引き返したと思う.] |
| 11:40 | [天候] | この時点では完全な風雪.国境稜線上は特に風が強い.[11時くらいまではトレースは残っていただろう.それ以降は雪のため消えてしまったのではないか.] |
| 12:30
唐松と白岳の中間 |
[目撃] | 唐松から縦走してきた3人(男2人・女1人)パーティーと会う.<熊本学園大学パーティーが白岳で会ったパーティーと思われる.> |
| [ルート状態] | この時点でトレースはみるみる消えていってしまう状態. | |
| 14:00
唐松山荘 |
[行動] | 唐松岳は登らずに、下山に移る. |
| [天候] | 完全なホワイトアウト.山荘手前の岩場で風速20m/sくらいあったと思う. | |
| 16:15
八方山荘 |
[行動] | 下山 |
[その他コメント]
北尾根にとりつくかどうかの判断は難しい判断だったと思う.同じ状況でもパーティーの目的等によっても判断は異なってくる.(ただ、自分の場合、ガイドとしてでなく山岳会の仲間と行っても、北尾根を中止していた.)
21日は悪天だったが、行動できない程ではなかった.
桑原清氏聞き取り結果
聞き書き日時: 1999年4月8日−16日
聞き書き相手: 桑原清・沢村・井出・今村・磯谷
(敬称略)
パーティー構成: 10名(男性6名・女性4名)
備考 :
山岳ガイド桑原氏(千葉県在住)と、他にアシスタントガイドが1名
パーティーの中で比較的余裕のあった方4名を他に紹介してもらい、聞き書きの補足をした
| 登山計画(予定) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭 |
| 3月21日 | 地蔵の頭−五龍岳−地蔵の頭 |
| 3月22日 | 地蔵の頭−(テレキャビン)−神城(下山) |
| 登山コース(実際) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭 |
| 3月21日 | 地蔵の頭−五龍岳−地蔵の頭 |
| 3月22日 | 地蔵の頭−(徒歩)−神城(下山) |
| 時刻・場所 | 行動・天候・ルート状態・目撃情報・他 | |
| 3月20日 | 神城−地蔵の頭 | |
| 14:00
地蔵の頭 |
[行動] | テント設営. |
| [天候] | 高曇りで、山は見えていた.白馬、八方尾根、唐松岳は見えていた記憶がある. | |
| [ルート状態] | クラスト状態で、足首くらいまでしかもぐらないので、歩きやすかった. | |
| 3月21日 | 地蔵の頭−五龍岳−地蔵の頭 | |
| 4:30
地蔵の頭 |
[行動] | 天場出発.五龍岳から遠いところにベースを張ったので早めに出た. |
| [天候] | 高曇りで、気温は暖かかった.[南風が雲を押し上げているので、気温が低くなってきたら悪くなると思った.]視界は良く、山は見えていた.入山前までの気象情報で、天気が下り坂にあるのは把握していた.[午前中が勝負だと思っていた.天気図で日本の南に前線があったので、悪天は続くと思っていた.
二つ玉低気圧が来るとの予想はしていない.] |
|
| [ルート状態] | 昨日と変わらない. | |
| 遠見尾根 | [目撃] | まだこれから出ようとしているパーティーが結構いた.カクネ里方面へ降りるトレースは意識していなかったので、記憶にない.テントはエスパースかゴアライトが多かったが、それ以上のことは覚えていない.(沢村) |
| 10:00?
白岳の登り(頂上前鞍部) |
[天候] | 白岳を登っていると、気温が下がってきた.[天気が崩れてくると思った.] |
| 11:00?から11:30?
五龍山荘 |
[行動] | 疲労した女性2人は小屋で待機することにし、休憩後、残りのメンバーで山頂を目指す. |
| [天候] | 出発時になって、五龍山頂に雲がかかってきた.この後、どんどん下り坂. | |
| [目撃] | 降りてくるパーティーは結構いた. | |
| 12:30?
五龍岳山頂 |
[天候] | 吹雪いていた.視界はあまりない.40−50mくらい.[山頂まではもつと思っていたので、予想より崩れるのがちょっと早かった.] |
| [目撃] | 2人組のパーティーがいた.一人が若く、一人は年配.
<熊本学園大学パーティー>
自分達の5分後くらいに登ってきたパーティーがいたが、その後会っていない.<あいまいな記憶で、始めは2、3人のパーティー、荷物は大きかった様な気がするという情報だったが、その後、割とはっきり記憶している人(井出氏)が見つかり、以下のように語った(他メンバーの磯谷氏もそれを肯定).2人パーティー、大きな荷物ということで、平松・石原パーティーである可能性、または両名を目撃している可能性も考えた.>そのパーティーは男2人女2人で、若くなく、サブザックだった.(井出) <奈良岳志会の可能性.ただし奈良岳志会は4人パーティーだが、男3人女1人.奈良岳志会パーティーだった場合、当パーティーの正確な登頂時刻は12時頃と考えられる.> 山頂より少し前で、鹿島槍から縦走してきた男2人女1人の割と若いパーティーに会った.<連絡先不明.> 視界が悪く、意識もしていなかったので、鹿島槍方面からのこのパーティーがつけたトレースの有無は覚えていない.トレースがあっても、降雪のため不明瞭になっている状態. |
|
| 五龍岳直下のコル | [地形] | 雪は浅く、雪洞は掘れない.トラバースに入っていく地点はわかりずらい.そこから3,4ピッチトラバースして、その後もコンティニュアスで行った |
| 五龍岳下り | [天候] | 雲の中から出ていく感じで、少し良くなる.視界は少し良くなった.後尾から50mのロープの先にいる人が見えていた.(沢村) |
| [ルート状態] | すぐにトレースが消えてしまう.自分達が登ってきたトレースはなくなっていた.新雪でトレースが消えていたので、足を置くときに気をつけないと流される.見通しが効かないので、ルートファインディングが難しい. | |
| [目撃] | 登ってくるパーティーはいなかった.10人いたので、下山には時間がかかった.[以上のことから、自分達がほとんどいちばん最後のパーティーだと思う.]<頂上付近で目撃されたという4人パーティーだが、五龍岳往復のパーティーだったとすると、下りでトレースがどんどん消えてしまうので、当パーティーよりさらに時間がかかった可能性もあるだろう.> | |
| 14:00過ぎ?
五龍小屋 |
[天候] | 横なぐりの雪.さらさらとした雪だった.(沢村) |
| 白岳 | [目撃] | 男2人女1人のパーティーが地図を見ていた.<志水氏および熊本学園大学パーティーからの聞き取りから考えると、唐松から縦走してきたパーティーと考えられる.> |
| 遠見尾根 | [目撃] | 行きはずいぶんあったテントが、かなり減っていた.(沢村) |
| [天候] | 雪はかなり降っていた.[翌日下山するパーティーはラッセルで大変だろうと思った.]風は強かったが、耐風姿勢を取るほどではなかった.(沢村)[大きな低気圧が来ていると認識していたが、二つ玉低気圧だとは思っていない.] | |
| 17:00
地蔵の頭 |
[ルート状態] | 50cm以上雪が積もっていた.テントがつぶれそうなほど. |
| 夜半
22−23時? |
[天候] | 風がかなり強くなってきた. |
| 3月22日 | 地蔵の頭−(下山) | |
| [行動] | テレキャビンが止まっていたので、歩いて下りた. | |
| [天候] | 21日に比べ、雪は大したことがないが、風がものすごく強かった. | |
[その他コメント]午前中良くて、午後に悪くなり下りでやられる、典型的な遭難しやすい天気だった.
ビバークに自信がなければ、暗くなったりしてからでも、なんとしてでも小屋まで行こうとするだろうから、(平松・石原は)ビバークに対する自信があったのかもしれない.<ビバーク日時が21日であった場合の話.>
熊本学園大学山岳部聞き取り結果
聞き書き日時: 1999年4月1日18時から
聞き書き相手: 岡本大助[熊本学園大学山岳部](敬称略
)
パーティー構成: 橘利昭(55歳・熊本学園山岳部OB]
岡本大助[20歳・熊本学園大学山岳部2年生]
備考:橘氏は雪山経験あり何度かこの山域にも来たことがあるとのこと.
3/22の下山中に疲労凍死で亡くなる.
岡本氏は雪山始めて.
| 登山計画(予定) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見(C1) |
| 3月21日 | 大遠見−五龍岳−大遠見(C2) |
| 3月22日 | 大遠見−地蔵の頭−(下山) |
| 登山コース(実際) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見(C1) |
| 3月21日 | 大遠見−五龍岳−大遠見(C2) |
| 3月22日 | 大遠見−地蔵の頭付近(ビバーク) |
| 3月23日 | 下山 |
| 時刻・場所 | 行動・天候・ルート状態・目撃情報・他 | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見 | |
| 地蔵の頭 | [天候] | 曇り.風はほとんどない. |
| [ルート状態] | 雪にズボズボ埋ったりはしなかった. | |
| 小遠見 | [行動] | 昼食を取る. |
| 14:00?
大遠見付近 |
[行動] | 1パーティーがテントを張っていたので、その近くにテントを張る.場所はよくわからない.翌日起きると、もっと白岳寄りの場所にテントが沢山張ってあるのに気が付いた.(20日に気付かなかったのか、それともそれらのテントは自分達の後から張られたのかはわからない.)<翌日、下山中の横浜山岳会と思われるパーティーに会っているので、大遠見の中遠見寄りだと推測される.>携帯電話(NTTドコモ)はかろうじて受診できる状態だった. |
| [目撃] | 黄色い2人用テントは見たような気もする.他パーティーの人間の外見に関する特徴は記憶にない. | |
| 3月21日 | 大遠見−五龍岳−大遠見 | |
| 5:30
大遠見付近 |
[天候] | 起きたときには鹿島槍が見えていた。 |
| 8:00?から8:30?
天場発 |
[天候] | 起きたときより、雲が多くなっていた |
| [トレース] | 意識していない. | |
| 10時くらい?
白岳山頂 |
[天候] | 白岳山頂では薄日が差し、橘氏が写真を取った記憶がある.雪も降っていなく、風も少しだけ.この後辺りから風とガスが出てきた.少し雪も降ってきた. |
| 10:30?
五龍山荘 休憩 |
[天候] | この時点では小屋の辺りにはそんなに雪は積もっていなく、五龍も見えた. |
| 五龍岳登り | [天候] | 途中から風もガスもちょっとひどくなってきた.この後は悪くなる一方. |
| 12:00?か13:00?
五龍岳山頂 |
[行動] | 天気が悪いので、すぐ下降に移る. |
| [目撃] | 千葉在住のガイド<桑原氏>の率いるパーティーに追い付かれ、一緒に降りる.また、山頂手前で2、3人のパーティーに追い抜かれたような気がする.記憶があいまい.このパーティーとはその後会っていない.橘氏と「あのパーティーは降りてこないね」と話した記憶あり. | |
| 五龍岳−五龍山荘 | [ルート情報] | トレースが埋もれて、足を置くときに積もった新雪の上を滑り、2回ほど滑落(5−6m)したが、すぐピッケルで止まった.岩が露出している箇所は何箇所かあった. |
| 五龍山荘 | [ルート情報] | 山荘まで戻ってきたときには、ヒザくらいまで雪があった. |
| 白岳 | [目撃] | 山頂で唐松から縦走してきたパーティーと一緒になり、天場まで戻る. <志水氏が白岳−唐松の間で会ったパーティーと思われる.> |
| [ルート情報] | 白岳山頂から下るときは北側に雪庇が出ていたよう. | |
| 16:00
大遠見付近 天場着 |
[天候] | 雪深め.埋もれるほどではなかったが、雪のためテントの判別がちょっと困難だった.風はテントの入り口側(南側?)から吹いていた |
| 夜 | [天候] | 風は歩けないほど、とまではいかないが、もうこの頃にはかなり強かった22日よりはちょっとはまし、という程度 |
| 3月22日 | 大遠見−地蔵の頭付近 | |
| 5:00
大遠見付近 起床 |
[天候] | 風はテントの入り口と反対側(北側?)から吹いていた.橘氏がオーバーミトンを片方飛ばされる.詳しい状況は不明. |
| 7:00
出発 |
[行動] | テントはたたまず置いていくことにした. |
| [天候] | 視界はほとんどなくホワイトアウト状態.目も開けていられないような状態.風もものすごく強く、トレースもなく、すぐに引き返し置いてきたテントに戻って入る. | |
| 8:30? | [行動] | 8−9人(2パーティー)が下りて来たので、一緒について天場を出る. <このパーティーの片方は横浜山岳会だと思われる.> |
| 小遠見 | [行動] | 小遠見で横浜山岳会と思われるパーティーが故障者のためビバーク.残りの4人パーティーと先に行く. |
| 12:00過ぎ?
地蔵の頭付近 |
[行動] | 地蔵の頭から300m程度小遠見寄りの場所で橘氏が歩けなくなる.4人パーティーは先に行った.ルートを探しにいって戻ってきたら、橘氏の意識はかろうじてある程度になっていた.手袋と帽子を外しており、もうろうとした意識の中で取ってしまったらしい.ゲレンデスキーに来ていた別のOBに連絡をしたが、留守電になっていて、連絡をとれなかった. |
| 14:00前? | [行動] | 奈良岳志会パーティーが通りかかり、一緒にビバークをする. |
| 夜 | [天候] | 夜になり悪天は少しずつ治まってきたよう. |
| 3月23日 | 地蔵の頭付近−下山 | |
| [天候] | 天候回復.下山 | |
増井行照氏聞き取り結果
聞き書き日時: 1999年4月13日・15日
聞き書き相手: 増井行照
(敬称略) パーティー構成:
3人(男性2名・女性1名)
備考: 山岳ガイド増井氏の登山ツアー
| 登山計画(予定) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見山(C1) |
| 3月21日 | 大遠見山−五龍岳−大遠見山(C2) |
| 3月22日 | 大遠見山−地蔵の頭−(テレキャビン)−神城(下山) |
| 登山コース(実際) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見山(C1) |
| 3月21日 | C1−五龍岳−大遠見山−地蔵の頭−(テレキャビン)−神城(下山) |
| 時刻・場所 | 行動・天候・ルート状態・目撃情報・他 | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見山 | |
| 9:00
地蔵の頭 |
[天候] | 曇り、風はなかった.雪は、ほんのちらつく程度. |
| [目撃] | 地蔵の頭より少しあがったところで、若い感じの二人パーティーに追い越された.荷物が大きく、縦走より少々重装備だなと思ったが、詳しくは覚えていない.ヤッケの色なども記憶にない.以後そのパーティーにあったという記憶なし.<石原・平松パーティーの可能性もあり> | |
| 10:30
小遠見山 |
[ルート状態] | 小遠見山まではくるぶしくらいまでずぼる程度だったが、それ以降は雪がしまっていて、歩きやすい.トレースも尾根上についていた. |
| 11:45
大遠見山 |
[行動] | 大遠見山手前に幕営 |
| [目撃] | 遅れて2 人パーティーが幕営.年配の男性と若い男性の組み合わせ.この時期の装備としては軽めだな感じた.<熊本学園大学山岳部パーティーの可能性> | |
| 3月21日 | 大遠見山−五龍岳−大遠見山−地蔵の頭−(テレキャビン)−神城 | |
| 5:50
大遠見山幕営地 |
[行動] | 出発. |
| [天候] | 街の灯もみえて視界はあった.高曇りといった感じ.風はなかった. | |
| [目撃] | 大遠見山から南へ下りる尾根へのトレースはなかったと思う.[ただ、白岳付近がかなりクラストしていたので、尾根も、いくらかはクラストしていたのではないだろうか.トレースがあっても見えなかったのかも知れない.]<志水パーティー(北尾根を計画)より早く現地を通過> | |
| 9:30
五龍岳山頂 |
[天候] | 剣岳が見えて、視界はあった. |
| [目撃] | 北尾根を含むバリエーションルートは気にしていて、見たけれど、トレース、人影には気がつかなかった. | |
| 五龍山荘 | [天候] | 剣方面がガスに覆われはじめていた. |
| 11:00頃
西遠見山付近 |
[天候] | 南よりの風が吹きはじめた. |
| 11:00過ぎ | [ルート状態] | 雪も降りはじめ大遠見頂上あたりのトレースは、消えては、また人が歩いてつく、という様な感じだった. |
| 11:45
大遠見山幕営地 |
[天候] | 風が強くなってきており(10−15m/sの風?)、テントが揺れていた.雪も降っていた. |
| 12:00 | [行動] | 下山を決定.[20日の夕方のラジオで、天候が下り坂なことを知っていたし、西遠見山付近ではじまった降雪、風が、現に強くなっている.お客さんの希望も、今日中に下りれる時間だということを告げると、疲れているし下山したい、ということだった。この時点で、二つ玉低気圧の存在、またそれが、急速に発達することは知らなかった.] |
| 13:00 | [行動] | 下山を開始. |
| 15:30
神城 |
[行動] | テレキャビン山麓駅着. |
[その他コメント]バリエーションをやるようなパーティーは2つほど、見たが、3−4人パーティーだった.前に雨が降っていたと聞いていたし、雪がしまっていたので、積雪があったら雪崩れるなと思った.
横浜山岳会聞き取り結果
聞き書き日時: 1999年3月31日18時から
聞き書き相手: 横浜山岳会桐ヶ谷豊(CL)・吉田次男(SL)
パーティー構成:
男性4名・女性1名
備考: CL、SL共に雪山経験豊富
メンバーの1人が凍傷にかかった
| 登山計画(予定) | |
| 3月20日 | 神城泊 |
| 3月21日 | 神城−遠見尾根(C1) |
| 3月22日 | C1−五龍岳−遠見尾根−鹿島部落−(下山) |
| 登山コース(実際) | |
| 3月20日 | 神城泊 |
| 3月21日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見(C1) |
| 3月22日 | C1−小遠見−地蔵の頭−地蔵の頭下のリフトの管理小屋でビバーク |
| 3月23日 | 下山 |
| 時刻・場所 | 行動・天候・ルート状態・目撃情報・他 | |
| 3月20日 | 神城まで | |
| 神城 | [天候] | 雪は降っていないし、気温も低くない. |
| 3月21日 | 神城−地蔵の頭−大遠見 | |
| 9:00
山頂駅 |
[天候] | 雪なく風もほとんど感じない.稜線見えたが、稜線からガスが下りてきていた. |
| 9:30
地蔵の頭 |
[天候] | 稜線で雪煙があがっているのが見える.地蔵を越してから小雪が降ってきた |
| [ルート状態] | しっかりしたトレースがあった. | |
| 11:00
小遠見山 |
[天候] | ガスが出てきた.視界はまあまあで、行動の制約はない |
| 13:00
大遠見山の 小遠見寄り |
[行動] | テントを設営.設営場所を考慮しなかったために、後で3回除雪することになった. |
| [天候] | どんどん下り坂で悪くなる一方.設営し終わる頃には風混じりの雪.翌22日の五龍岳アタックはこの時点ではもう考えていない.明日の撤収とその夜の風対策しか考えていない.風向きは南西方向からで、夜中の0時過ぎるまではまでは変わらず.風は時々息をついていた.[→上の稜線上でも作業はできたかもしれない.] | |
| [ルート状態] | トレースは埋もれてしまっていた. | |
| 14:00 | [天候] | 本格的な悪天になる. |
| 15:00 | [天候] | 分岐を間違えそうになった3人パーティーがいた.[→分岐が判別できないほどガスが出ていたと思う] |
| 夜 | [天候] | 何回か除雪しなければいけないほどの雪.(17時と20時と0時に除雪) |
| 0:00 | [天候] | この時刻を境に風が北からの強烈な風に変わる.以後、雪は飛ばされてしまい、除雪の必要はなかった. |
| 3月22日 | 大遠見−地蔵の頭−リフト管理小屋(ビバーク) | |
| 8:00
大遠見 天場発 |
[天候] | 依然北からの強烈な風.この日は1日中、風向きは北からだった.視界は10mくらい.ブリザード状態.気温はそれほど低いと感じなかった.[風は強いと思ったが、樹林帯だし下りれる自信はあった.] |
| [行動] | 先に下りるパーティーはいなかった.自分達は大遠見にくる時に、標識竿を立ててきたので、先頭に立って下りた. | |
| 遠見尾根下降中 | [天候] | 風は息をほとんどつかない.行動するより止まっている時間のほうが長かった.耐風姿勢でも膝を折られるほどの風.これほどの悪天候は雪山経験34年で始めて.(吉田)[上に人がいるとは思えなかった.]雪はラセッルで苦労しない雪.ルートを時々見失う. |
| 小遠見 | [行動] | 凍傷にかかったメンバーのためビバークを試みる. |
| [天候] | 4人掛かりでもツェルトを押さえるのが大変な風. | |
| [ルート状態] | バーン状.小遠見から白馬村側に雪庇があり、雪庇を避けるためにトレースの少し下を歩く. | |
| [目撃] | 小遠見あたりでキスリング姿の年配の男性が後ろを歩いていた.<熊本学園大学山岳部OB・橘氏のことだと思われる.> | |
| 13:30
地蔵の頭 |
[行動] | ルートがわからなくなるので、リフト沿いに下降. |
| 14:30
リフト監視小屋 |
[行動] | ビバークをする. |
| 3月23日 | リフト管理小屋−神城(下山) | |
| 朝
テレキャビン山麓駅 |
[目撃] | 遭難した熊本のパーティーに会った.奈良のパーティー<奈良岳志会>に助けられたと聞いた |
[その他コメント]朝鮮半島に低気圧があった時点までしか天気図をフォローしていなかった.
予想より荒れだしたのは早かった(6時間前後).
二つ玉低気圧は予想していなかった.
確かに吹雪くかとは思っていたが、あれほどの風は考えていなかった.
奈良岳志会聞き取り結果
聞き書き日時: 1999年4月4日・5日
聞き書き相手: 尾崎・田中・島崎
(敬称略)
パーティー構成: 4人(男性3名・女性1名)
備考: 22日下山時に熊本学園大学パーティーを救援
| 登山コース(実際) | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−西遠見山(C1) |
| 3月21日 | C1−五龍岳−西遠見山(C2) |
| 3月22日 | 西遠見山−地蔵の頭付近(ビバーク) |
| 3月23日 | 下山 |
| 時刻・場所 | 行動・天候・ルート状態・目撃情報・他 | |
| 3月20日 | 神城−(テレキャビン)−地蔵の頭−大遠見山 | |
| 9:48
ゴンドラ 終点出発 11:55 小遠見山 |
[天候] | 曇天.視界中程度(数百m). |
| [目撃]
天候 [ルート状態] |
登山者多数.
少量の降雪あり。 はっきりしたトレースがあるが、踏み外すとひざまで潜る. |
|
| 11:45
大遠見山付近 |
[ルート状態] | 多少の跡はあるが、この付近からトレースがほとんどなくなる.(クラストしていたため.ただし、横に踏み出すとひざまでもぐってしまう)左に向かっているトレースには気付かなかった.あったとしても埋もれてしまったのではないか |
| [天候] | 雪がちらつく.五龍岳は見えない. | |
| [目撃] | テントは3張ほど. | |
| 14:30
西遠見山付近 |
[行動] | 標高2268−2172mの間の南斜面に雪洞を掘る. |
| [天候] | 五龍岳は見えず | |
| [行動] | 天気図は取っていない.ラジオの電波の入りが悪く、気象通報も聞けなかった.入山前の週間天気予報で明日悪くなることは知っていた. | |
| 3月21日 | 西遠見山−五龍岳−西遠見山 | |
| [天候] | 曇り.風はほとんどなく、五龍・鹿島がはっきり見える.
[天気が悪くなることは知っていたが、行って帰ってくる時間はあるだろうと判断.] |
|
| 8:00 | [行動] | 出発. |
| 西遠見山雪洞 | [目撃] | 西遠見山付近にテント5,6張.黄色のゴアライトの記憶なし. |
| 白岳直下 | [行動] | 練習がてらアンザイレン. |
| [天候] | 雪が舞い始める. | |
| 10:10
五龍山荘 |
[目撃] | 山荘には4パーティー位いた.引き返すパーティーもあった. |
| [天候] | 降雪と風が強まる. | |
| [行動] | 初心者が2人いたため、ザイル確保で山頂へ向かう | |
| 12:07
五龍岳山頂 |
[天候] | 少し前から雪、風ともに急に激しくなってホワイトアウト. |
| [目撃] | 視界20−30m.そのため鹿島槍からのトレースやこっちへ向かってくるような登山者の姿は全く分からない. | |
| [ルート状態] | 帰りのトレースは、激しい雪と風でほとんど消えている.歩くそばからトレースが消えていく.大きな岩などはでているが、北側トラバースのトレースは埋もれている.わずかな跡を探しながらザイル確保しつつ五龍山荘へ.[下山するときに、登ってくるパーティーはなかったので、自分達が最後のパーティーではないかと思う.] | |
| 14:55
五龍山荘 |
[天候] | ホワイトアウトの状態で白岳からのルートファインディングにてこずる.左(北)からの強風.ただし対風姿勢をとる必要はなかった(22日程強くない). |
| 17:15
西遠見山付近雪洞 |
[目撃] | 途中テントは2つ残っていた.色は記憶にない. |
| [天候] | 強風降雪激しい.新雪30−40cm. | |
| 18時か
19時 |
[行動] | この日はラジオで天気予報を聞く.天候が悪いことだけを知る. |
| 3月22日 | 西遠見山−地蔵の頭付近(ビバーク) | |
| 6時ころ | [行動] | 強烈な風雪で外に出られない. |
| 10:30
西遠見山雪洞 |
[行動] | 雪洞の天井がおちかけてきたので、脱出する事にする. |
| [ルート状態] | 一面クラスト.微かにワカンかアイゼンの跡が残っていたので、それを頼りに進む.[あの風雪で残っていたのだから、自分達より少し前に別のパーティーが通ったのではないか] | |
| 12:45
小遠見山 |
[天候] | 13時頃が風が最も強く、立っていられない程.歩いては止まる、を繰り返しながら進む. |
| [行動] | 小遠見山と地蔵の頭との中間のJPで誤って左に進む.(足跡がたくさんあったため)
少し下で、熊本学園大学のパーティーと出会う. |
|
| 14:30地蔵の頭付近 | [行動] | ビバーク決定.雪洞でビバーク. |
| 3月23日 | 地蔵の頭付近−神城(下山) | |
| 4:00 起床 | [天候] | 2時30分頃まで風強し.そこから風が弱まってきた. |
| 5:50 出発 | [天候] | 快晴 |
| 7:30 | [行動] | 下山 |
船橋勤労者山の会聞き取り結果
聞き書き日時: 1999年4月15日22時から
聞き書き相手: 本田浩
(敬称略)
パーティー構成: 2名(男性2名・41歳と25歳)
| 登山計画(予定) | |
| 3月20日 | 大谷原−東尾根−一ノ沢ノ頭(C1) |
| 3月21日 | C1−鹿島槍北峰−赤岩尾根−大谷原(下山) |
| 登山コース(実際) | |
| 3月20日 | 大谷原−東尾根−一ノ沢ノ頭(C1) |
| 3月21日 | C1−鹿島槍北峰−冷池山荘(C2) |
| 3月22日 | C2−赤岩尾根−大谷原(下山) |
| 時刻・場所 | 行動・天候・ルート状態・目撃情報・他 | |
| 3月20日 | 大谷原−東尾根−一ノ沢ノ頭 | |
| 8:00
大谷原出発 |
[天候] | 曇りだった.風はなかったと思う. |
| 東尾根 | [ルート状態] | しっかりしたトレースがついており、歩きやすい. |
| 11:30
一ノ沢ノ頭 テント設営 |
[天候] | 一ノ沢ノ頭に着いたときには、ガスっていた.視界20mくらい?.
テントを張ってからは雪が降っていた.どのくらい積もったかは覚えていない. テントから出なかったので、あまりその後の天候はわからない. |
| [目撃] | 着いたときには、1パーティーがテントを張っていた.
最終的には5パーティーくらい、ここにテントを張った. |
|
| 夕方 | [天候] | ガスが晴れて、山が見えた.
風は特に記憶に残っていないので、あまり吹いていなかったと思う.[天気図やまわりのガイドの話から、21日の昼過ぎまではもつと思った.] |
| 3月21日 | 一ノ沢ノ頭−鹿島槍北峰−冷池山荘 | |
| 6:30
一ノ沢ノ頭 天場出発 |
[天候] | 高曇り.山は見えた.
北峰に出るまで、風はなかったと思う. |
| [ルート状態] | トレースがついていた.軽快なキックステップ、ところどころザイルを出しながら登っていく感じ.北峰までかかった時間は予定通り. | |
| 11:00過ぎ
北峰 |
[天候] | 北峰の手前からすでに天気が崩れてきていた.ガスって、すぐ隣のテング尾根が見えなかった. |
| 北峰→南峰→冷池山荘 | [天候] | 風が強い.不慣れなので、何度も耐風姿勢を取らなければなかった.慣れていた人でも、時折耐風姿勢を取っていた.風は右側(北西?)から吹き付けていた.積雪があり、ラッセルは多い所でヒザ上くらい.トレースはかすかに残っているくらい.風が強い所は雪は飛ばされてしまっている.予想以上に時間はかかった.予想より早く崩れたと思ったが、パートナーは予想通りだと語っていた. |
| 14:00
冷池山荘 |
[天候] | 風が少し弱まり、天候が和らいだ気がしたので、進むかどうか迷った.
視界も山荘まで来た時点では、結構あったと思う.[トレースが埋ってルートの判別がむずかしいこと、疲れていたこと等から小屋に泊まることにする.]その日のうちに下山したパーティーもいるよう.明日になったら天候がましになる見込み特にはなかった.ガイドは明日はもっと悪くなると言っていた. |
| 3月22日 | 冷池山荘−赤岩尾根−大谷原(下山) | |
| 6:00
冷池山荘出発 |
[ルート状態] | 前日までに雪がかなり積もっていた.ヒザ上から股下くらい. |
| [行動] | 冷池にいたパーティーでまとまって下りることにした. | |
| 赤岩尾根の頭 | [ルート状態] | 赤岩尾根に入るところのルートファインデングが難しい.懸垂で降りているときに、上のパーティーが起こしたのか小さい雪崩が起きた.雪質は軽く、被害はなかった.高千穂平に行くまでに倍くらい時間がかかった.←ラッセル・ルートファインディング・懸垂に時間を取られた. |
| [天候] | 赤岩尾根に下りて行くと、風は大分弱くなった. | |
| 14:00
大谷原 |
[行動] | 下山. |
テレキャビン聞き取り結果
聞き書き日時 "1999年4月1日,4月2日,4月10日
聞き書き相手 倉科
[白馬五竜スキー場テレキャビン職員]
(敬称略)
ゴンドラの運行規定では、風速が
15m/s以上
注意
20m/s以上
営業運転不可
25m/s以上
運転不可 となっている.
| 3月20日 | |
| [目撃] | 入山パーティーが多く、特に遭難した2人と思われる人物に心当たりはない. |
| 3月21日 | |
| [天候] | 曇りまたは雪がちらつく程度.良い天気ではなかったが、通常の範囲内.
スキー場は夕方まで通常通り営業していた. |
| 3月22日 | |
| 概況 | この日スキー場は閉鎖
(朝方は下の方だけ動かしていた).12年勤務して、今まで4回しかなかったくらいのレベルの悪天
ホワイトアウトしていた. 雪質は軽かった. 天候が悪化したのは、下では22日の午前4時か5時くらい |
| 7:50 | 風速20m/s以上なので、営業運転はできない状態.
営業再開に備えてゴンドラをまわして、従業員4名を上にあげた. スキー場は夕方まで通常通り営業していた. ゴンドラは運転不可能な風となる. 以後、終日運転不可.上部の従業員は全員歩いて下った. |
| 9:30頃 | |
| 14:50−15:00 | 自動計測ではなく目視で、気象データを測定している.
データにある風速45m/sは、この時刻に10分間、風向、風力計を見て、記録したもの.計測していた時間以外に、もっと強い風が吹いていたことはありうる. テレキャビン上部のリフトでは、風速50m/s以上を記録したと言っていた. |
[気象データについて]
スキー場の気象データはすべて白馬村役場に提出することになっている
他のスキー場のデータも白馬村に問い合わせればわかるはず.
各スキー場には、日本気象協会からの72時間予報が入る。<72時間後の予想天気図では二つ玉低気圧は予想されていた。>
雑誌「山と渓谷」のFAX情報サービス(0990-6-12125)では翌々日の9時までの予想天気図が手に入る.ただし毎日18時更新
[当日昼12時の実況天気図・翌日9時・翌々日9時の予想天気図].
[テレキャビンの運搬能力]
12秒に1台(8人乗り)運行する.1時間で2400人を運搬できる能力はある.
8時15分が始発.山に登る人はほとんど前の方に並んでいるが、仮に後ろの方に並んでいたとしても、それほど出発が遅れることはないだろう.
[気象の傾向]
今年の冬は天候が不順で、非常に移り変わりが激しい.しかも、週末の度に悪い.
積雪は年々減少傾向.今年の冬の累計積雪量は、6m程度である.以前はその倍以上あった。
リフトの支柱の高さは、過去十年間の積雪の統計から算出するが、最近のものは以前に比べると、1m以上低くなっている.
計画通り北尾根に入ったのか?
→北尾根に入った可能性が高い。
理由:
・ 聞き込みに協力してもらった他パーティーの中では、2人の可能性のある目撃情報は地蔵の頭でのものを除いて、得られていない。
・ 聞き込みに協力してもらった他パーティーの中では、3月21日に遠見尾根での目撃情報がない。
・ フル装備で発見された(遠見尾根経由で五龍岳を往復するだけの場合には、通常アタックキャンプを設営して、軽い荷で行動する)。
・ 20日に入山しているので遠見尾根経由で稜線まで二日かかるとは考えにくい。(遠見尾根経由で五龍岳に向かった他パーティーは21日中に稜線から降りている。彼等の足ならさほど時間がかからない)。
北尾根は技術的に無理な計画ではなかったか?
→同程度の技術が必要とされる雪山の経験は豊富であり、彼等の技術では問題ない(第10節の山行略歴参照)。
同じ北尾根を計画していた志水パーティーと日程の計画が違うが無理はなかったか?
→計画通りの日程で行動する必然性は無い。下山までの計画日数は同じであるから無理ではないだろう。
いつカクネ里・シラタキ沢出合に下ったのか?
※計画書からは下降点が大遠見山付近からか西遠見山付近からか特定できなかった。
a)21日6:15以降ではないか。
理由:
・ 20日午後1時前後には大遠見山山頂付近の下降点では、トレースが目撃されていないので、それ以前には谷に下降していないことが考えられる。反証:
・ 20日午後はガスで視界が利かず降りるのはむずかしい。
・ 大遠見山山頂付近の下降点では21日6:15まで谷に降りるトレースは目撃されていない。 20日夕方〜21日朝にかけては雪が降っていないようなので、トレースが降雪で消えることはないと考えられる。
・ この日の内に北尾根に取り付いていないと、その後の天候を考えると説明が苦し
い。
・ 西遠見山など他の場所から下降した可能性もある。
b)20日午後ではないか。
理由:
・ 20日には下降点までのトレースがしっかりあったので、彼等の足なら相当早い時間に下降点に着いただろう。その後谷に下降した可能性がある。反証:
・ 22日は天候が悪く恐らく動けないだろう。平松の時計の記録から、22日には稜線にいた可能性が高いので、そのためには21日中に北尾根を抜け稜線に上がっている必要がある。その為には20日中に北尾根に取り付いているとすると時間的に説明がし易い。
・ 北尾根には随所にビバークポイントがある。
・ 大遠見山からのトレースが無くても西遠見山から下降した可能性もある。
・ 20日の日中は視界が悪く谷に降りられるかどうか分からない(志水氏の話では余程下降ルートの地形に熟知しているのでなければ、まず降りられないとのこと)。21日以降の行動は?
・ 20日までの数日間は降雪がないので雪の状態が良く、北尾根の時間がさほどかからなかった可能性がある(同じ山域の天狗尾根ではクラストしており、ラッセルに困っていない)。反証:
・ トレースが残っていれば更に容易になる。
・ 22日に北尾根を抜けたとすれば、風の強い稜線上を事故現場まで歩かなくてはならないが、22日は行動できるような天候ではなく、また仮に動いたとしても、北尾根の頭から事故現場までは長く(天候が良くて3〜4時間)、恐らく耐えられるようなものではないだろう。
・ 21日昼前までは天候が比較的良く、午後になって急変した事を考えると、午前中にかなりの場所まで到達し、更に悪化していく天候の中、残りの時間で小屋を目指した可能性がある。
・ 21日中ギリギリまで粘ったが、天候・視界の悪化と日暮れでザックの置いてあった地点が行動の限界だったのか。
・ 予定ならば北尾根を抜けるのに丸1日以上かかることに加え、21日午後の天気は悪天であることから、21日中に遭難現場までたどり着くのは時間的に難しい。b)22日に事故現場までたどり着いた可能性。
・志水氏は遠見尾根のトレースを外れるとスネまでもぐり、三月としては雪の状態が悪かったので、北尾根は時間がかかると判断している。
・仮に21日中に装備発見場所まで辿り着いたとすると、22日朝まで夜を通してのビバークをしなくてはならないが、夜のビバークで使われるはずのヘッドランプはパッキングされたままであった。
・予定ならば北尾根を抜けるのに丸1日以上かかること、及び21日午後の天気を考えると、21日中に遭難現場までたどり着くのは時間的に難しい。反証:
・すぐ隣の八方尾根の気象ロボットデーターを見る限り、21日18時〜22日5時の間、一時的に風が弱く、行動できた可能性がある。
・夜を通してのビバークならヘッドランプを出しているはずだが、パッキングされたままであり、21日からのビバークをしていないのではないか。
・22日7:50にわざわざ時計を高度計モードにしている事から、行動していた可能性がある。
・基本的には耐風姿勢を取っても体が揺らぐほどの悪天であり、行動できたのか。
・22日に動いていたとすると暴風雪の中での行動となるが、ハーネスも付けていないのは不自然である。
←しかし、ビバーク中にも係わらずセルフビレイを取っていなかったので、行動中 にハーネスを付けていた必然性はない。
c)23日に事故現場までたどり着いた可能性。
理由:
・可能性は捨て切れない。反証:
・ 23日は風が強いものの晴れており、ビバークする必要性が低い。23日に動いていたならば下山できたはず。
ビバーク態勢にあったのか
→21〜22日にかけてビバーク態勢にあった可能性がある。
理由:
・装備の置き方疑問点:
・シュラフが残っていた(人が寝ていたので雪が解け、シュラフと雪面が氷着していたと考えられる)。
・日付は天候から推察。
・テントが無いのは何故?
←強風で飛ばされてしまった可能性がある。
・ヘッドランプ・シュラフカバーを出していないのは何故?
←出せるような状況ではなかった?(悪天の中でテントが無いなど)
・21日ならどうしてG?・G?のコルでビバークしなかったのか?
←前述のような行動の限界にあれば不思議ではない。
事故発生の状況は?
特定できるほどの証拠がなく、また目撃者もいないため不明。