五龍岳遭難事故に寄せて
慶應義塾大学アルペンフェライン山岳会OB会
会長福田耕三
平松君、石原君のご冥福をお祈り申し上げます。ご遺族の皆様には今の気持ちはいかばかりかとお慰めする言葉もありません。ただ御一緒に両君のご冥福を祈るばかりです。
遭難の第一報を受け大いに慌てました。即刻、救助隊員を派遣すべく緊急手配を行い、両君の先輩、同期、後輩の6名による救助隊を、即日大町に向かわせました。両君が高い山の技術を備え、充分な経験もあり、強い意志の男たちである事から、最悪の事態は考えてもみませんでしたが、刻々と入る現地情報から不安が募るばかりでした。このような結果に終わってしまったことは、誠に痛恨の極みです。
どんなに言葉を選び、両君の行動を擁護しても遭難に対する世間の糾弾は厳しく、我々もこの言葉を真摯に耳を傾けざるを得ません。個人的には敢えて、今回の両君の行動を無謀だとは考え難く、避け難い偶然の事故だったのではと思っております。しかし取り返しのつかない事故となってしまった事は事実で、そこには要因がある訳です。
遭難の後始末として、慶応義塾大学アルペンフェライン山岳会とそのOB会は関連山岳会と協力して事故原因をの解明に全力を挙げて来ましたが、今もって原因を確定するには到っておりません。このことは御遺族の皆様にとりましても気懸かりな事でありましょうが、我々にとりましても同様であります。
平松君、石原君の夢の一つにきっと遥かヒマラヤの峰々への山行の事があったと思います。この思いを実らせる事なく逝ってしまわれたことは両君にとりまして大きな心残りだと悲しい思いが致します。
この遭難報告書の作成に当たられた関係の皆様、特に秀峰登高会、慶応義塾大学バックパッキングクラブの皆様にはこの様に深く掘り下げた報告書を纏めていただけたことを感謝しつつ、今後の山行の為の貴重な資料として広く活用される事を願っております。
我々現役学生、OB会は今回の事を糧として、今後より注意深く着実な山行を心懸ける事を改めて誓いました。
慶応義塾大学アルペンフェライン山岳会一同、及びOB会を代表して、君たちが大好きであった自然の中で、どうぞ安らかにお休み下さる様、謹んでお祈りいたします。
平成11年8月記
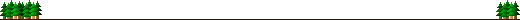
秀峰登高会ご挨拶
二人の若者がこの世を去ってしまいました。残念です。悔しいです。そして、その命の重さが我々にとても重く、深くのしかかってきています。
3月23日午後、家族からの連絡で彼等の山行を知り、24日昼には遺体発見の連絡、そして25日夜、何も語ることのない平松君との対面。でも、私には『みんな山で死なないで』と語りかけているように思われてなりませんでした。
彼等の突然の死で、ご両親、兄弟、友人、同僚、岳友とそれぞれの人々が、その胸を痛め、何故、どうしてとの思いを募らせたこととおもいます。
我々もその思いから、彼等の足跡を追うため、5月2日・3日と彼等の計画通りに北尾根から五龍岳をトレースしてみました。彼等のザックが置かれていた場所に着き、彼等が発見された雪面を見渡しましたが、『どうしてこの場所で』との思いを強くするのみでした。やはり天候、体調、気力等々、現場にいる人間でない限りわからないのが山であり、対自然とのかかわりなのでしょう。
そのような山と対峙している我々は、これから先、各人の山行を安全に実現させていくことへの問題意識を持ち続けなければいけないと再確認しています。
残念にも私自身、山で多くの友人、知人を亡くしています。しかしそのことが持つ意味を身近なものとして全会員に認識させていたでしょうか。この5年間大きな事故も無く、新入会員も増え、各人がそれぞれの山行を行ってきていました。救助訓練等は定期的に行っていましたが、何も無かった事に流されていたのは事実です。
今回の遭難も含めて再度会員で話し合い、その中で現在の会の弱点が多く指摘されました。そして現在会員としての約束事の文書化や、事故が起こった場合の対応マニュアルの作成を行なっています。
あくまでも山登りをするために集まった山岳会なのですから、山へ行く自由な雰囲気は失いたくありません。しかし会員が、自分の目指す山登りを安全に成し遂げる為の、必要最低限の約束事は決めなければいけないし、また、山に対する危機感は持ち続けなければいけなのです。
今回この報告書の作成に関しましては、慶應義塾大学アルペンフェライン山岳会OB会(岳酔会)、慶應義塾大学バックパッキングクラブOB会の方々の、精力的な活動によるものであり、当会一同感謝しております。
また、長野、富山両県警の方々には、その捜索と事故処理において大変お世話になりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
ここにあらためて平松君、石原君の御冥福をお祈り致します。
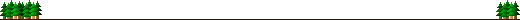
これからも自然とともに
慶應義塾大学バックパッキングクラブOB一同
平松君が慶應大学バックパッキングクラブの門を叩いたのは平成5年秋のことでした。翌年には山岳系サークルのアルペンフェラインクラブにも籍を置き、アウトドア活動の領域を着実に広げていきました。
彼が入部したての頃に同行した経験を持つあるOBの弁ですが、平松君が3年生の時に再び同行した沢登プランで、2年前の彼とは違う大きく成長した平松君がそこにいたことを思い出すそうです。
多くのOBやOGが大学卒業とともにアウトドア活動を引退したり休眠したりする中、彼は社会人になって以降も率先して休暇日を作り、好きな山やフィールドに出かけていろんな顔を見せる自然との出会いを楽しんでいたようです。
私たちアウトドア活動に親しんだ者たちは皆、自然を愛し、自然に触れることに無上の喜びを感じます。
自然の持つ温かみに触れたとき、人の心を癒し元気にしてくれる何かを私たちは受け取ります。
自然の厳しさに直面したとき、自分の小ささに打ちひしがれる気持ちになったりもします。
また、そうした感覚や体験を共有財産にすることで、私たちは年齢・性別に関わりのない、幅のある付き合い方を学んだりもします。
平松君や石原君を失った今も、彼らが残してくれたことに私たちの思いはまだまだ至りません。
しかし、彼らがこれまでに触れてきた自然は今も変わらないままそこにあり、これからも私たちへの問いかけを忘れないことでしょう。
私たちは少しずつでもいいから、これからも自然に向き合い続けていきたいと思います。
私たちが自然を愛し続ける限り、そして、その問いかけに耳を傾け続ける限り、きっと多くのことを自然は語ってくれるのではないかと思います。
『これからも自然とともに。』
この私たちの基本姿勢にこれからも変わりのないことを改めて確認し、その誓いを胸にお二人のご冥福をお祈りいたします。
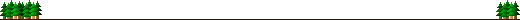
生い立ちの記
平松茂雄
小さい時から、好きなことには夢中になる性格だった。4歳の時東京から大和市に引っ越してきた。新築祝いに頂いたお金でプラスチック製の池を買い鯉を飼った。餌をやったり循環器の掃除をしたりした。その時の鰹と金魚が何匹か大きくなっていまでも小さな池で泳いでいる。中学の時野良猫が迷い込んできた。この猫が次々と子供を生み多い時には、十数匹の猫がいた。その頃守が作った複雑種まりないわが家の猫家系図が残っている。
小学校のいつ頃からだったかはっきりしないが、鉄道に夢中になった。プルー・トレインとその動力車のEF58に人気があった時代で、東京駅と上野駅のプラット・フォームで駅弁を食べながら、夜遅くまでプルー・トレインが出発する写真を撮るのについていったことが何回かあった。長男が厚木高校に入学したお祝いに、ボーナスを全部はたいて家族5人でプルー・トレイン「はやぶさ」に乗って西鹿児島まで行き、その先の最南端の国鉄駅・西大山で記念撮影をした後、熊本から豊肥線のスイッチバックを経て阿蘇へ行き、高千穂線で一番高い鉄橋を歩いて渡ったりした。帰りも宮崎からブルー.トレインで帰った。
その後は「青春十八」切符を使って、一人で全国各地に出掛けるようになり、浜松、大官、高崎などの機関区の動力車の展示、鉄道用品・部品の頒布会などにもよく行った。ブルー・トレインの寝台マットを夏の暑い盛りに一人で抱えてきたこともあった。記念切符、今では珍しくなった硬券切符、手書きの切符その他鉄道関係資料が押入に山ほど残されている。肥薩線人吉のループ線の写真を撮りに行ったとき、自分で葉書を出して予約して泊まった民宿「いけす」の家族と親しくなり、毎年年賀状の交換をしていた。
小学校時代には時々ずる休みをして親を心配させたが、二人の兄が慶応大学に入学したことから、自分も負けられないとの負けず嫌いの性格からか、高校2年の秋頃から突然勉強をし始めた。その頃からだと思うが、日本の歴史や文化に興味を持つようになり、いつの間にか奈良や京都にも行くようになった。臼杵の石仏、瀬戸内海の新三等、兵庫県の鶴林寺の聖観音など、親も行ったことがないところまで行っている。牧渓の展覧会や益田鈍翁の回顧展などを見るなど、古美術に関する関心には玄人好みのところがあった。子供の時は歩くことを嫌がったのが、いつから山に登るようになったのか。大学2年の秋、次男がアルペンフェラインで山に登っていたことがきかっけのようである。残された登山記録を見て、よくもたくさんの山に登ったものだと、そのバイタリティーに驚く。冬山や春山に登るからには遭難は付きものと思ってはいたものの、いざ現実となると、いいようのない衝撃で?った。僅か25歳の短い人生ではあったが、大勢の人達とお付き合い頂き、好きなことをして完全燃焼したことがせめてもの慰めである。
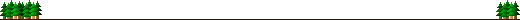
皆様に感謝して〜自分の人生を一生懸命生きた健哉〜
石原 ひろ子
今回このような事故を起こし、県警及び山岳警備隊の方々始め、救助に当たって山まで駆けつけて下さいました皆様、遠くでご心配下さいました皆様には、ただただ感謝の気持ちと申し訳ない気持ちで一杯です。
以前、山岳警備隊の方々の書かれた文を読ませていただいたことがあり、息子と「くれぐれも気を付けて、迷惑をかけないようにね」と話したことがあり、本人も実際大怪我をして警備隊の方が救助している場面をも見たことがあり、「気を付けねば」と言っていたのに、まさか自分の子があの様な姿となって上まで揚げて頂く事になろうとは、夢であればと願うばかりです。
大学に進んで念願の山岳サークルに巡り合った日の嬉しそうな顔が忘れられません。まさかこんなに山にのめり込んでしまうとは思いもよらず、ただ「気を付けて行ってらっしゃい」という軽い気持ちで送り出したのが冬山へ行き、山スキーを覚え、沢登り、そしてフリークライミング。四季を通し休む事なく暇を見つけると生き生きと出かけていく後姿、自然の素晴らしさ、小さな花々、山に棲む鳥や獣たち、そして過酷さ、それらの事を戻った時真っ黒に日焼けして、目の周りだけ白くなった顔で話してくれたのが夢のようです。やっと社会人となり仕事の楽しさも少しずつ覚え、山だけじゃない事も分かり始めホッとしたのも束の間、やっぱり休みがとれると山へ。山好きはしょうがないと諦め、あの子の山行きに家中が巻き込まれ、バタバタと引っかき回されていました。あの子の嬉しそうな様子が私にも嬉しく、今日は戻る、という日には朝から待ち遠しく好きなものを作り果物や飲み物を用意して「下山したよ、何時頃帰るよ」との電話を待っていたものです。
まさか五龍岳が最後になるなんて。
「雨が降って危ないよ。雪崩気を付けてね」と止めて止める訳がないので軽い注意をしただけ。いつもとは違い「送ってくれ」の一言もなく静かに出かけてしまい、気が付いたときは「あら、いつのまに出かけたの」という静かな出発。あんな姿になって戻ってくるなんて。
バタバタとまた家中巻き込んで「山行くぞ、買物してきて」と元気な声で言って欲しい。天気を調べて、危ない時は動かず、安全な所に隠れていてね。今迄ずっとそうしていたでしょ。危険な事も数々あったし、敗退しちゃったと戻ってきたじゃないの。
無理したのじゃないよね。気を付けたよね。あなたを信じていたのに。
不幸にしてこんな結果になってしまいましたが、OBの方々始め現役の方々、山のお友達や社会人となってお世話になった皆様に心より感謝しています。
若い皆様方も夢を求め冒険して自分を鍛え、ともすれば無謀な事もするでしょうが、あなたを失うと悲しむ人がたくさんいる事を知って下さい。自分の人生を一生懸命生きているあなたの逞しさを見るのが嬉しくって、安全なだけの道を進んで長生きするより、精一杯生きたのだから、頑張ったんだから、幸せだったと思いたいです。
そして私達はこの子に、こんなに信頼できる素晴らしい仲間が、惜しんでくれる友がたくさんいて下さったということを忘れず、生きる支えとしたいと思います。
ありがとうございました。
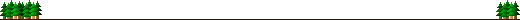
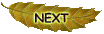
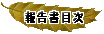
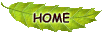
![]()
![]()
![]()
![]()